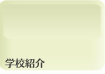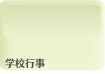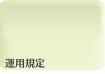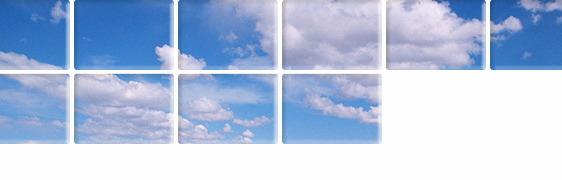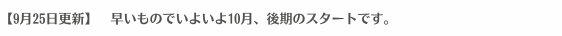
弟子屈町立弟子屈中学校いじめ防止基本方針を掲載します。ぜひ一読ください。
平成26年度 弟子屈町立弟子屈中学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識・基本姿勢
「いじめは、どの学校でも、どの学級でも、どの生徒にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の生徒が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校をつくるため、「弟子屈中学校いじめ防止基本方針」を策定した。
≪いじめ防止のための基本認識≫
1 いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ。
2 いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行う。
3 いじめ問題は学校の在り方が問われる問題である。
4 関係者が一体となって取り組む必要がある。
≪いじめ防止のための基本姿勢≫
1 学校、学級内にいじめを許さない、見過ごさない雰囲気をつくる。
2 生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
3 生徒、教職員の人権感覚を高め、生徒と生徒、生徒と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築く。
4 いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決する。
5 いじめの早期解決のために、当該生徒安全を保証するとともに、学校内だけでなく保護者・地域、関係機関との連携を深める。
2 いじめの未然防止のために
(1)生徒に対して
①生徒一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
②わかる授業を行い、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育てる。
③思いやりの心や生徒一人一人がかけがえのない存在であるといった命の大切さを、道徳の時間や学級の指導を通して育む。
④「いじめは決して許されないこと」という認識を生徒が持つよう、様々な活動の中で指導する。
⑤見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら先生や友人に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。
⑥学級や生徒会の活動において、自主的、主体的にいじめ防止に取り組むよう指導する。
(2)教員に対して
①生徒一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、生徒との信頼関係を深める。
②生徒が自己実現を図れるよう、すべての子どもが生きる授業を日々行うことに努める。
③生徒の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級の指導の充実を図る。
④「いじめは決して許さない」という姿勢を教員が持っていることを様々な活動を通して生徒に示す。
⑤生徒一人一人の変化に気づく、敏感な感覚をもつよう努める。
⑥生徒や保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。
⑦「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等、「いじめ問題」についての理解を深める。特に自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
⑧問題を抱え込まないで、管理職への報告や学年・同僚への協力を求める意識をもつ。
(3)学校全体として
①全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
②いじめに関するアンケート調査を定期的に実施し、結果から生徒の様子の変化などを教職員全体で共有する。
③「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について教職員の理解と実践力を深める。
④校長が、「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許さない」ということと、「いじめ」に気づいた時にはすぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを生徒に伝える。
⑤いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、生徒会が企画し実施する「いじめ根絶集会」など、いじめ絶滅に向けた取組を行う。
⑥いつでも、誰でも相談できる体制の充実を図る
(4)保護者・地域に対して
①生徒が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。
②「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、保護者懇談会、道徳授業公開、PTA総会、学校評価委員会等で伝え、理解と協力をお願いする。
3 いじめの早期発見・早期解決に向けて
(1)早期発見のために ⇒「変化に気づく」
①生徒の様子を、担任をはじめ全ての教員で見守り日常的な観察を丁寧に行い小さな変化を見逃さず、気づいたことを学年や全体で共有する場を設け、より多くの眼で当該生徒を見守る。
②様子に変化が見られた場合、教師から積極的に働きかけを行い生徒に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には教育相談等により事情を聞き問題の早期発見を図る。
③いじめアンケート、生徒アンケート、”i-Check”などを実施し、生徒の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して生徒との信頼関係を深める。
(2)相談ができる
⇒「 誰にでも」
①いじめに限らす、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを伝えていく。
②いじめられている生徒や保護者からの訴えには、親身になって聞き、生徒の悩みや苦しみを受け止め、生徒を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝えるとともに、いじめられている生徒に自信や存在感をもてるよう励ます。
③いじめに関する相談を受けた教職員は、管理職に報告するとともに学年や生徒指導連絡会等を通して、全体で情報を共有する。
(3)インターネットいじめに対応
⇒ 「モラル指導とチェックを」
①児童生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。
②ネットパトロールを定期的に行い、早期発見・早期対応できる校内体制を整える。
(4)早期解決を
⇒ 「傷口は小さいうちに」
①教職員が気づいたかあるいは生徒・保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく、傍観者も含め構造的に問題を捉える。
②学校として組織的な体制のもと、事実関係を把握する。
③いじめている生徒に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まずいじめをやめさせる。
④いじめがどれほど相手を傷つけ、苦しめているかを認識させ、いじめの行為にいたる気持ちを聞き、その生徒の心の安定を図る指導を行う。
⑤事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について、学校と連携し合っていくことを伝えていく。
⑥犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携し対処する。
4 いじめ問題に取り組むための組織
(1)「いじめ対策防止委員会」の設置
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ対策防止委員会」を設置し、原則として月1回開催し、いじめ事案発生時は緊急開催する。
①構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーとし、必要に応じて校長はその他の有識者を招集する。
②委員会の活動は、いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)、いじめ防止に関すること、いじめ事案に対する対応に関すること、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること等とする。
(2)生徒指導交流会の開催
月1回、全教職員で問題傾向を有する生徒について、現状や指導の状況等を情報交換し、指導内容・方法等を協議、確認する。
(3)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの事実把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
①いじめの早期発見に関する取組に関すること
②いじめの再発を防止するための取組に関すること
5 重大事態発生時の対応
「重大事態」とは、いじめにより
1 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(子どもが自殺を企図した場合等)
2 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い(年間30日を目安、又は一定期間連続して欠席している場合)
※生徒や保護者からいじめで重大事態に至ったという申し立てがあった場合。
①弟子屈町教育委員会に重大事態が発生した旨を報告する。
②弟子屈町教育委員会と協議し、当該自体に対処する組織「いじめ問題対策協議会」を設置し、事実関係を明確にする調査を実施する。(北海道いじめ問題等解決支援外部専門家チーム、警察、生徒相談所、SC,SCW等)
③「いじめ問題対策協議会」を中心とし、事実関係を明確にするための調査し、情報収集と事実確認を行う。
④調査結果を踏まえ、生徒や保護者への事実関係及び情報を適切に提供するなど必要な措置を行う。
(金品の授受、暴行等については、第28条に則り行う。警察への通報、出席停止等を含む。)
6 年間計画の策定と計画的な取組
4月
「いじめ対策委員会」の取組
その他全職員での取組
・いじめ、問題行動等に対する学校基本方針の確認
(未然防止への取組の提示、発見⇒解決までのルートの提示等を強化徹底)
・教育相談の取組の検討
・学校評価アンケートの分析と2学期の取組の検討
・学校の基本方針、関係機関担当者の確認
・いじめ、問題行動等に対する学校基本方針の説明(PTA総会、学級活動)
・教育相談の実施、事後の情報交換
・いじめアンケート①
・学校評価アンケートの実施
・「道徳の時間」の授業公開
・1学期の反省と2学期の目標の設定
5
6
7
8
・校内研修ための資料等の準備
・教育相談の取組の準備
・学校評価アンケートの分析と3学期の取組の確認
・夏休み後の児童・家庭の情報交流
・情報モラル講習会の実施(校内研修)
・いじめアンケート②
・教育相談の実施、事後の情報交換
・学校評価アンケートの実施
・2学期の反省と3学期の目標の設定
9
10
11
12
1
・総合質問紙「i-check」の分析
・次年度の取組の検討
・総合質問紙「i-check」の実施
・冬休み後の児童・家庭の情報交流
・保護者に対するケータイ教室(新入生説明会、警察官の招集)
2
3
定期的な取組
・生徒指導実態交流(職員会議)
・生徒の一日の振り返り(日常観察、朝・帰りの会)
・いじめ把握のためのアンケートの実施(6月,11月)
・学校ネットパトロールの実施(4月、6月、8月、11月、1月、3月)
・弟子屈町生徒指導連絡協議会、釧路生徒指導連絡協議会等への参加
生徒に係る取組
・一学校一運動の内容検討、いじめ撲滅宣言の採択(生徒総会)
・いじめ根絶集会(生徒総会)
・弟子屈町いじめ撲滅サミットの参加
・いじめ撲滅!メッセージコンクールの作品応募(標語・ポスター)
・北海道どさんこ☆子ども会議の参加
〒088-3215 北海道川上郡弟子屈町美里1丁目3番1号
TEL:015(482)2071 FAX:015(482)2061
E-mail : teichuu@educet.plala.or.jp
所在地 : http://yahoo.jp/KWZK1I
|